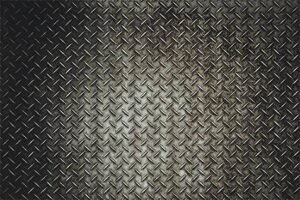[ロンドン 20日 ロイター] – 米連邦準備理事会(FRB)はついに金利市場を掌握できるようになるかもしれないが、その警戒心を忘れているように見える活況な銘柄に警戒の目を向けているのは確かだ。
FRBのジェローム・パウエル議長は今週、年内の緩やかな利下げに関するFRBの12月のメッセージが、懲りた金利先物と米国債にようやく耳を傾けられたと確信し、2日間の議会証言に臨む。
しかし、AI の影響でウォール街の株価指数が新記録を更新し、半導体メーカーや人工知能ブームに関連するほぼすべての銘柄が狂乱に近い勢いで上昇していることを少し見ただけでも、彼は次のような思索に心を戻さざるを得なくなるだろう。 前任者はアラン・グリーンスパン。
グリーンスパン氏は1996年12月、FRBの歴史とその責務に関する長々とした講演の中で、株式市場の「不合理な熱狂」と中央銀行がそれに対して何をすべきかについて意見を述べ、市場の一時的な混乱を引き起こした。
同氏の比較的議論の余地のない答えは、バブルのような株価はFRBの懸念ではない――価格設定の誤りが経済全体に影響を与えるか、バブル崩壊の脅威が金融全体の安定を不安定にする危険がない限り、というものだった。
しかし、今や有名になったこのフレーズは心に刺さり、当時泡沫のように見えた世界株価を数日間ひっくり返した――その年を通じて政策を堅持してきたFRBが利上げで株式バブルを刺激するつもりかもしれないという基本的な仮定に基づいてだ。
グリーンスパン氏は当時、「金融資産バブルの崩壊が実体経済、その生産、雇用、物価の安定を損なう恐れがなければ、中央銀行家として私たち中央銀行家は心配する必要はない」と述べ、1987年の市場からの広範な影響は見られないと指摘した。 クラッシュ。
「しかし、資産市場と経済の相互作用の複雑さを過小評価したり、現状に満足したりすべきではない」と同氏は付け加えた。 「したがって、バランスシート全般、特に資産価格の変化を評価することは、金融政策の展開に不可欠な部分でなければならない。」
もし彼がこの最後の一線を忠実に守ってさえいれば、その後10年間彼が主宰したさらに大きな銀行と住宅ローン担保債務バブル、つまりFRBの直後に壊滅的な世界的影響をもたらして崩壊したバブルは避けられたかもしれない、と多くの人が主張している。 長官はオフィスを去りました。
おそらくパウエル氏にとっての教訓は、グリーンスパン氏が潜在的なリスクを認識し、それを相殺するためにほとんど何もしなかったということだ――1997年3月には小幅な利上げを実行したが、さらに18カ月間政策を再び据え置き、1998年には再び利下げを行った。
実際、当時この演説は大失敗とみなされていたにもかかわらず、株価はその後10日間で約4%下落しただけで、6週間以内に記録的な高値まで回復した。
そして、INGのクリス・ターナー氏が今週指摘したように、S&P500はその講演からその後3年間で倍増したが、そのピークは2000年のドットコムバブルの最盛期に過ぎなかった。最終的な破綻により3年間の弱気相場がもたらされ、指数は約7年かかった。 新高値を取り戻すには何年もかかる。
熱狂を再評価
しかし、市場の「熱狂」に対するグリーンスパン氏の見解は、パウエル氏とチームが直面している同様の状況を説明するものとしてここ数週間、多くの金融アナリストによって再び取り上げられている。
1991 年から 1996 年の期間と同様に、S&P500 は約 5 年間で 2 倍になり、10 年間でほぼ 3 倍になりました。
アトランタ連銀総裁のラファエル・ボスティック氏は先月、株式については明確には言及していないものの、経済全体の「蓄積された高揚感」がインフレを再び上昇させる可能性があること、そしてそれが利下げに対する同氏の慎重さをいかに強調しているかについて語った。
パンデミック後のFRB金利の上昇と長期借入コストの上昇により経済はある程度抑制されているが、債券市場は今年初めから再び若干引き締まったが、金融状況はより一般的には再び緩和しつつある。 株式市場のブームが復活。
例えば、米国の金融状況に関するゴールドマン・サックス指数は今月、2022年8月以来の最低水準にまで後退しており、11月以降の緩和幅151bpsのうち約94ベーシスポイントは株価の急騰によるものである。
米国の家計は現在、1980年代以来、貯蓄ポートフォリオにおける自己資本の割合が最も高く、裕福な家計への資産効果は相当なものになる可能性がある。
例えばイングランド銀行の政策委員であるキャサリン・マン氏は先週、裕福な家計が金利上昇の影響を比較的受けておらず、依然として旅行やレストラン、娯楽に散財していることが一因で、中央銀行当局はサービスインフレを制御するのに苦労していると指摘した。
したがって、バブルのリスクは別として、株価急騰の影響を懸念する説得力のある政策上の理由があるかもしれない。
しかし、それは見方によって異なります。
AI投資ブームは生産性の飛躍的な向上を促し、経済が過熱することなくより速く拡大し、景気を減速させるための金利引き上げの必要性を回避できるため、中央銀行はAI投資ブームを応援すべきだと多くの人が主張している。
そして、インベスコのチーフ・グローバル・マーケット・ストラテジスト、クリスティーナ・フーパー氏は、株式市場全体のバリュエーションが好調に見えるのは、単に「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる超大型株のわずかなリードによるものだと考えている。これらの超大型株は、今後1年間の利益成長率がそのほぼ5倍になると予想されている。 残りのS&P500企業493社のうち。
希望に支えられて上昇した1990年代後半のインターネット株とは異なり、これらは真の基礎的な基盤であると彼女は述べた。
「これは『非合理的な熱狂』ではなく、むしろ『合理的な熱狂』に近い」とフーパー氏は書いた。
パウエル氏が、今や評判が悪くなったFRBの先人をはっきりと真似したいとは考えにくいが、彼なりの独特のやり方で、事態を少しでも沈静化させようと考えているのかもしれない。
ここで表明された意見はロイターのコラムニストである著者の意見です。